住民税を納付せずに放置していると、役所から注意を引くような黄色や赤など、派手でカラフルな封筒が届くことがあります。開封すると、「納税催告書(のうぜいさいこくしょ)」という文字が。
催告書も役所などから納税を促す目的で発送される書類ですが、督促状とは役割が違う書類になります。
どの段階で届くのか、対応しないとどうなるのか――。
元徴税吏員の経験をもとにわかりやすく解説します。
催告書とは?【督促状との違い】
督促状は、法律に基づき送付される文書です。本来の納期限を過ぎても納付が確認できない場合、督促状は必ず発布しなければならないこととなっています。
一方で、納税催告書は自治体の判断で発行される「注意喚起」や「要求」にあたる書類で、法律上、必ず出さなければいけない書類というわけではありません。
本来は督促状を発布しても納付の確認ができない場合、財産の差押えを執行しなければいけないところなのですが、自治体としても一件一件滞納が発生する度に差押えをしていては時間の効率が悪く、手が回らないのが現状です。
そこで、自治体は財産調査をしている時間などを利用して、独自の催告書を送ることがあります。封筒が派手でカラフルなことが多いのも、とにかく目立たせて「中身を確認しないと危険だ!」と思わせるための創意工夫によるものです。
自治体の封筒って、だいたい同じ見た目で大事な書類かどうかぱっと見で分からず、ついつい放置してしまうことってありますからね。
書面の文面も自治体によって異なり、「このまま納付がなければ差押えを実施します」など強い表現が使われることもあります。
この通知により、納付をうっかり忘れていた納税者や、書類にびっくりして今後きちんと納めるようになってくれる効果を期待しているわけです。
督促状が差押えを含めた滞納処分のための「法的なスタートライン」だとすれば、催告書は自主的な納付を期待する自治体からの「最後のお願い」と言えます。
実務体験例
私が現役の頃は、まだ催告書が役所の他の封筒と同じようなもので発送していたため、他の郵便物と紛れ込んでしまうことから思うような効果が得られませんでした。
そこで、封筒の色を黄色などの目立つ色のものに変えました。さらに催告書も複数回送るようにして段階的に封筒の色が赤に近づくようにしたところ、驚くほど相談や納付に繋がりました。
「役所がこんな怖がらせるようなことをしていいのか?」とお叱りもありましたが、その効果の高さから、今では多くの自治体でも見られるようになりました。
催告書が届くまでの流れ
- 納期限を過ぎる
- 督促状を発送(10日以上経過しても納付・連絡なし)
- 催告書の送付 → ここまでで、ほとんどの方の納付が済むか、納付のメドが立つ
- 場合により複数回の催告書の送付(その裏で財産調査など、滞納処分の準備を進める)
督促状から催告書までの期間は自治体によって異なりますが、滞納発生から1〜2か月以内に届くことが多いでしょう。
催告書を無視するとどうなる?
この書類まででおよそ99%の納税者の方が税金を納めるか、相談等により納付のメドが立っていることになります(税金の種類によりますが)。
自治体としても、残り1%の方については、書類で納付をお願いしても納付する気のない方と判断します。催告書を発布することは、本来の業務である滞納処分をせざるを得ない案件はどれか探し出すという、一種のふるいにかけることをしているわけです。
催告書を無視すると、原則として次は「差押予告通知」や「差押えなどの滞納処分」に進みます。
すでに猶予期間はほとんど残っていないため、放置は非常に危険です。
催告書が届いたときの対応方法
- まずは速やかに役所へ連絡しましょう(来庁してもいいですが、電話の方が確実です)
- 一括納付が難しい場合は、分割での納付を認められる場合あります
- 担当者と一緒に、現実的な納付計画を立てられます
💡 補足:知り合い職員への相談が気まずい場合
窓口対応が不安な場合は、個室やブースでの相談を希望できる場合があります。
「人目につかない場所で相談したい」と伝えれば、柔軟に対応してもらえる自治体も多いです。
催告書に書かれている内容の見方
催告書の内容は、自治体の考えや催告書の段階によって違います。
だいたいこのような内容になっているかと思います。
あなたが納めるべき税金について、督促等により自主的な納付をお願いしていましたが、現在まで納付の確認ができておりません。
つきましては、下記連絡期限までに納付を完了し、連絡してください。期限内に納付が難しい場合は、納税相談にも応じられます。
なお、連絡期限までに納付されない場合は、法律に基づき、差押え等の滞納処分を執行する場合がありますので、ご注意ください。
連絡期限 〇〇年△△月□□日
文書の構成の違いはあっても、
- 納付の確認ができていないこと
- 納付や連絡をいつまでにする必要があるかということ
- このまま納付が確認できないと、差押えなどの対象になること
などの内容となっているでしょう。
まとめ
- 催告書は法定文書ではなく、自治体が独自に発送する差押え前の“最後お願い”
- 開封してもらいたいので封筒は派手ににしていることがある
- 無視すると差押えに直結するリスクが高い
- 分納や相談の余地はまだ残されているため、届いた時点で必ず行動することが大切です
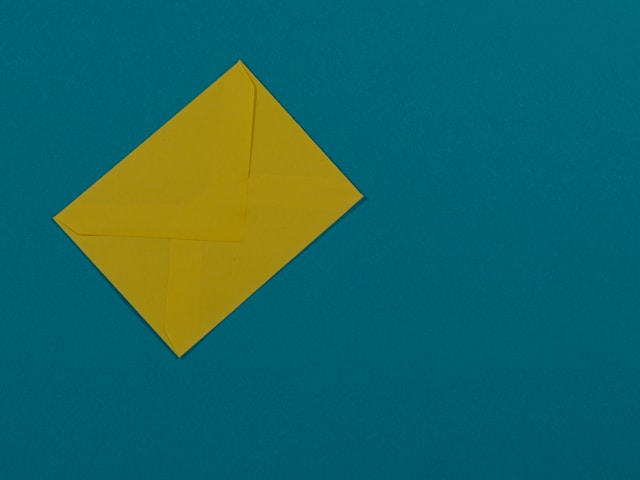



コメント