「住民税を滞納してしまった…。督促状が届いたけど、どうしたらいいのかわからない」
そんな不安を抱えてこの記事を読んでいる方も多いのではないでしょうか。
住民税を納めずに放置すると、延滞金が発生するだけでなく、最終的には給与や銀行口座の差押えにまで発展する可能性があります。しかし、早めに役所へ相談することで、分割納付(分納)や猶予などが認められる場合もあります。
この記事では、元徴税吏員の経験をもとに、住民税を滞納した場合の流れ・差押えのタイムライン・回避方法、そして再発を防ぐための生活改善のヒントまで解説します。
住民税を滞納するとどうなる?
最初は督促状から始まる
納期限を過ぎても住民税を納めなかった場合、まずは「督促状」が送られてきます。
これは「まだ納められていませんので、指定の期限までに納めてください」という最初の納税を求める通知です。督促状が届いた段階で指定期限までに納めれば特に問題はありません。
ただし、督促状は差押えの前提となる必須の手続きであり、ここからは差押え準備の段階に入っていると理解すべきです。
※督促状は、原則として納期限を過ぎて20日を経過するまでに送達され、その後おおむね10日後が納付期限に設定されます。
延滞金が加算される仕組み
督促状を無視して滞納を続けると、延滞金が加算されていきます。
- 延滞金は、当初の納期限を過ぎた日から計算が始まります。
- 毎年の特例基準割合に基づいて利率が定められます。
- 長期にわたる滞納では、元の税額を超えるほど延滞金が膨らむケースもあります。
※筆者は実務上、億単位で延滞金が加算されている事例を見たことがあります。
放置すると財産や給与の差押えへ
滞納を放置した場合、自治体は法律に基づいて財産の差押えを行います。
差押えの対象は以下の通りです。
- 給与、賃金、ボーナス、退職金
- 銀行預金(普通・定期)
- 不動産(土地・建物)
- 自動車
- 生命保険(解約返戻金)
- 貴金属やブランド品など動産
差押えが実行されると、勤務先や金融機関に滞納の事実が伝わるため、社会的信用を大きく損なうリスクもあります。
差押えまでの具体的な流れと日数
差押えまでの一般的な流れは次の通りです。
- 納期限を過ぎる
- 督促状が送付される
- 催告書や督促電話が来る(省略される場合あり)
- 差押予告通知が届く(省略される場合あり)
- 期限を過ぎても納付や連絡がなければ差押え執行
👉 自治体によって差押えまでの日数は異なりますが、督促状の発送からおおむね10日後〜数か月以内には差押えが行われることが多いです。
ある日突然「預金が引き出せない」「勤務先に連絡が入った」という状況になることも珍しくありません。
住民税の差押えを回避する方法
役所に相談して分割納付を申し出る
- 原則は一括納付が求められるが、事情を説明すれば分納が認められる場合がある
- 相談時は「収入と支出の状況」を整理しておくとスムーズ
- 給与明細や支出に関する証拠書類を求められることもある
納税誓約書や分納計画書を提出する
- 自治体によっては「納税誓約書」を記入する
- 計画に基づき納付を続ければ差押えを猶予してもらえる
- ただし条件は厳しく、短期間での完納や担保提供を求められることもある
差押えがされてしまっても諦めない
差押えは「財産を換金する前の段階」です。
- 滞納額を納めれば差押えは解除可能
- 分納計画がまとまれば手続き停止の余地がある
どうしても納められないときの選択肢
- 収支の見直しを行い、支払い可能な状態にする
- 家族などから一時的に借りて早期完納を目指す
- 他の借金がある場合は債務整理を検討する(※住民税自体は自己破産で免責されない)
- 消費生活センターや法テラスに相談し、弁護士・司法書士の助力を得る
滞納を繰り返さないためにできること
固定費の見直し
- 家賃の適正化
- スマホ・ネット代の格安プラン変更
- 保険料の見直し
支出管理と節約
- ポイント還元の高いクレジットカード活用
- 家計簿アプリでの収支管理
将来に向けた資産運用
- 新NISAやiDeCoを利用した積立投資
- 「納税資金を計画的に確保する習慣」をつける
まとめ
- 住民税を滞納すると延滞金が発生し、最終的には差押えに至る
- 差押えの対象は給与や銀行口座など生活に直結する財産
- 早めに役所に相談すれば、分割納付で回避できる場合が多い
- 差押え後でも納付や計画次第で解除可能
- 再発防止には「収支の見直し」と「資産形成による余裕づくり」が大切
👉 不安を抱えているなら、一人で悩まず、まずは役所や専門家に相談することから始めましょう。






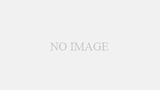

コメント