「いきなり銀行やゆうちょの口座が使えなくなった」「残高がゼロになっていた」
住民税などを滞納した際、生活へ大きな影響を与えるのが預貯金の差押えです。
この記事では、元徴税吏員の経験から、
- 預貯金差押えが行われるまでの流れ
- 口座凍結後の対応方法
- そして“差押え逃れ”が危険な理由
について、実体験を交えて解説します。
預貯金差押えとは?
預貯金差押えは、住民税などの税金滞納が納付されずに放置されると、それを回収するために行われる一連の強制手続きの一つです。
自治体によって金融機関等の口座が差押えられると、金融機関等は対象の口座残高の一部、または全額を一時的に凍結(ロック)します。
このとき滞納者の意思に関係なく、差押えられた口座内の残高が取立てられると、自治体に送金され、滞納税に充てられる仕組み(充当)になっています。
預貯金の差押えがされると、生活費の引き出しができないことや、支払い予定の振替えができずに、他の支払いまで滞ってしまい、日常生活に支障が出ることもあります。
預貯金差押えの具体的な流れ
住民税などを滞納すると、だいたい以下の流れで預貯金の差押えが進行します。
- 「督促状」が送付される
- 「催告書」が送付される(複数回の可能性あり)
- 「差押予告書」が届く(差押前の最終通知)
- 自治体が金融機関等へ預貯金差押えを執行する
- 口座が凍結され、本人が自由に出金することに制限がかかる
- 自治体が差押えした預貯金残高を取立てし、滞納税に充当する
この一連の流れのうち、②と③は省略されることがあり、差押え前に滞納者に事前告知されるとは限りません。
多くの場合、滞納者は口座が使えなくなったことや、通帳記載したときに初めて差押えを知るケースが多いのです。
【注意】「口座を移せば大丈夫」は大きな誤解
差押えされるかもしれないと考えている人の中には、
「別の銀行に給与を振り込んでもらえば差押えを避けられるのでは?」
「別の口座にお金を移して隠せばいいのではないか」
などと考える方がいます。
しかし、これは完全に間違っており、非常に危険な行為です。
徴税吏員は、金融機関だけでなく給与支払元や取引先などの情報を照会できる権限を持っています。
実際のところは、毎年の申告など役場に自然と集まる情報で、あなたの勤務先や取引先の特定は完了している場合がほとんどです。
おまけに、仮に別の銀行口座をお金を移しても簡単に特定できてしまいます。
どういうことかというと、わざわざ預貯金口座を差押えしなくても、収入元である給料等の差押えをした方が簡単だし確実なんです。
それでも給料等の差押えではなく、あえて預貯金差押えをしているということは何故でしょうか?
それは、会社などに連絡してしまうと、滞納していることが知られてしまうことや取引先からの信頼を失うなどの社会的リスクが発生するからです。
そんな中で、差押えを逃れようとしても口座を移してしまおうものなら
税金を逃れようとしている悪質な納税者と判断され、給料等の差押え・売掛金の差押えに切り替わり、結果的に勤務先や取引先に滞納が知られてしまう可能性があります。
傷口を広げるだけの可能性が高い行為です。
「差押え逃れ」を試みることで、
本来なら職場に知られずに済んだ滞納が社会的信用の喪失につながることもあります。
実務体験例
私が徴税吏員として担当していた案件で、過去に預貯金差押えをした方がいました。
その時は滞納税を完納することができたのですが、しばらくしてから新たな滞納が発生しました。
そこで、以前のように預貯金の差押えをしようと考えていましたが、残高がまったくなくなっていたんですね。
別の口座を作って給与の振込先を変更していたことはすぐに特定できました。
明らかに差押えを逃れようとしている行為なことは明白でした。
悪質な滞納者という判断をせざるを得ず、印象としては最悪でした。
このままだと同じことの繰り返しになり、毎回余計な時間と手間をかけることになりそうでした。
徴税吏員の仕事は滞納税の回収はもちろんですが、本質は自主的に納税していただける優良な納税者を一人でも増やすことです。
滞納していることや、差押えされることに慣れられてしまっては、徴税吏員としてもいつまで経っても本来の目的を達成することができません。
そこで、不本意ではありましたが、予告なく本人の勤務先へ訪問して給料等の差押えに移行することにしました。
結果として、勤務先に滞納している事実が知られてしまっただけでなく、毎月の給与から天引きして滞納税に充てられることになりました。
後からご本人に話を聞くと、「口座を移せば口座凍結や税金から逃れられると思った。まさか会社に来るとは・・・」とのことでした。
税金は必ず納めなければいけないものであり、自己都合で逃れることはできません。
この件は、かえって状況を悪化させる典型例です。
凍結された口座はいつ解除されるのか?
差押えされ、口座が凍結されても口座自体は使うことが可能です。
ただし、預貯金の残高のうち一部または全額が凍結されていることになりますので、使用に制限がされていると言った方が良いでしょう。
口座が凍結されたというのは、こんな状態です。
- 口座自体は使える。差押えが及んでいない残額は出金・送金・引き落とし可能
- 新たに入金した金額も同様に使用可能
- 滞納税額を納付し、完納すれば差押えが解除され、口座も元どおりになる
例えば預貯金の残高が30万円あり、滞納税額が10万円だった場合、差押えによって凍結されるのは30万円の口座残高のうち10万円のみです。
残りの20万円は凍結されていないので問題なく引き出したりすることができます。
ただし、自治体によってはいったん預貯金残高の全額30万円を差押えして、取立て後に残り20万円(残余金)を交付する方針を採っているところもあります。
預貯金差押えが執行され、取立て(金融機関から自治体への送金)が完了すると、金融機関側によって口座は自動的に凍結解除されます(というより、差押えしたものが無くなるので勝手に元どおりになるということですね。)。
ただし、滞納税や延滞金が完納されなかったり、分納約束を不履行している(守らなかった)ようなケースでは再び差押えが行われることがあります。
預貯金差押えを「一度きり」と考えるのは危険です。
差押えを防ぐためにできること
根本的な解決には、滞納税を一括で納付することですが、困難な場合は納税相談や分納計画の見直しが必要です。
差押えは、いきなり実行されるものではありません。
督促や催告の段階でしっかり対応すれば、回避できることがほとんどです。
✅ 早めに自治体へ連絡する
✅ 収入・支出の状況を正直に伝える
✅ 現実的な分納計画を立てる
自治体の担当者も、誠実に相談してくれる方には柔軟に対応します。
音信不通や無視を続けるような行為、口座を移して税金から逃れようとする行為は差押えなどの滞納処分に進行してしまいます。
まとめ
- 預貯金差押えは金融機関の口座残高の一部、または全額を一時的に凍結(ロック)する
- 督促状などの書類が届くと差押えなどの滞納処分の手続きが進行していることを意味する
- 口座を変えても差押え逃れにはならず、かえって職場や取引先に滞納が知られる
- 口座の凍結が解除されても、滞納税が残っていれば再び差押えのリスクがある
- 早期相談・分納提案が最善の対処法
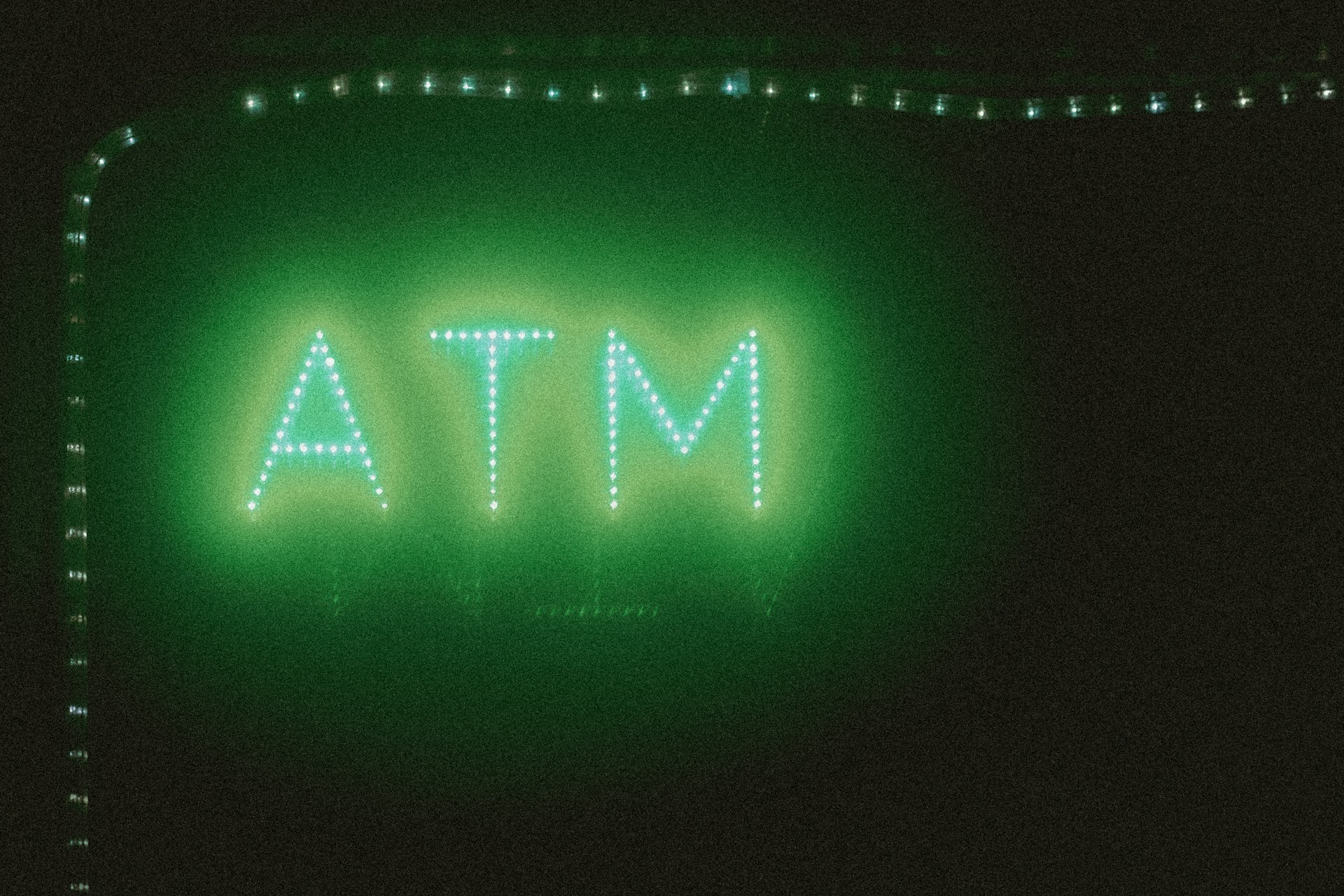


コメント